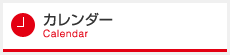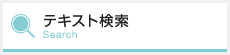秋田竿燈まつり
2018/08/03
こんにちは、佐々木です。
先日の日記で、竿灯祭りの事に少し触れさせていただきました。
毎年8月3日~8月6日の間、開催されます。
そうです。いよいよ始まりました!
ところで皆様、竿灯(竿燈)についてご存知ですか?
どんな事をしているのかやビジュアル的には良く知られているかと思います。
では、その理由や発祥はご存知ですか?
秋田県人としてお恥ずかしながら、私は存じませんでした。
ので!例によって例の如く調べてみました(笑)
正式名称は「秋田竿燈まつり」というそうで、重要無形民俗文化財だそうです。
竿燈そのものを稲穂に、提灯を米俵に見立て、額や腰、肩に乗せて豊作を祈るのだそうです。
東北の三大祭りのひとつ(青森のねぶた祭り・仙台の七夕まつり)であり、
日本三大提灯祭りのひとつ(福島の二本松提灯祭り・愛知の尾張津島天王祭)でもあるそうです。
もともとは笹や合歓木(ネムノキ)に願い事を書いた短冊を下げ、それを手に練り歩き、
川に流して真夏の邪気や睡魔を祓う「眠り流し」が原型といわれているそうで、
いつ頃から始まったのか、正確には不明との事です。
「眠り流し」が訛って「ねぶり流し」となったそうです。
竿燈そのものは、外町(町人町)に住む職人さんや商人さん達によって始められ、
お盆に門前に立てる高灯籠を持ち歩けるようにしたのが発祥と言われているそうです。
やがて灯籠も数十個と下げるようになって力自慢・力比べ的になり、
次第に力よりも技術を競うようになって、現在の形になったのだそうです。
旧暦7月7日の七夕行事とともに、旧暦7月15日のお盆を迎え入れるための
一連の行事として今の形になったのだそうです。
(ちなみに。
文中「竿灯」「竿燈」と同一単語に対して
複数の書き方をさせていただいている箇所がございますが、
調べた元の表記まま、です。)
県内の方はもちろん、県外からお越しの方も是非御覧になって下さい。
その迫力や腕前は、実際に見ると圧倒されますよ!?
先日の日記で、竿灯祭りの事に少し触れさせていただきました。
毎年8月3日~8月6日の間、開催されます。
そうです。いよいよ始まりました!
ところで皆様、竿灯(竿燈)についてご存知ですか?
どんな事をしているのかやビジュアル的には良く知られているかと思います。
では、その理由や発祥はご存知ですか?
秋田県人としてお恥ずかしながら、私は存じませんでした。
ので!例によって例の如く調べてみました(笑)
正式名称は「秋田竿燈まつり」というそうで、重要無形民俗文化財だそうです。
竿燈そのものを稲穂に、提灯を米俵に見立て、額や腰、肩に乗せて豊作を祈るのだそうです。
東北の三大祭りのひとつ(青森のねぶた祭り・仙台の七夕まつり)であり、
日本三大提灯祭りのひとつ(福島の二本松提灯祭り・愛知の尾張津島天王祭)でもあるそうです。
もともとは笹や合歓木(ネムノキ)に願い事を書いた短冊を下げ、それを手に練り歩き、
川に流して真夏の邪気や睡魔を祓う「眠り流し」が原型といわれているそうで、
いつ頃から始まったのか、正確には不明との事です。
「眠り流し」が訛って「ねぶり流し」となったそうです。
竿燈そのものは、外町(町人町)に住む職人さんや商人さん達によって始められ、
お盆に門前に立てる高灯籠を持ち歩けるようにしたのが発祥と言われているそうです。
やがて灯籠も数十個と下げるようになって力自慢・力比べ的になり、
次第に力よりも技術を競うようになって、現在の形になったのだそうです。
旧暦7月7日の七夕行事とともに、旧暦7月15日のお盆を迎え入れるための
一連の行事として今の形になったのだそうです。
(ちなみに。
文中「竿灯」「竿燈」と同一単語に対して
複数の書き方をさせていただいている箇所がございますが、
調べた元の表記まま、です。)
県内の方はもちろん、県外からお越しの方も是非御覧になって下さい。
その迫力や腕前は、実際に見ると圧倒されますよ!?